「なんとなく」選んだ本が、教えてくれたこと
「なんとなく」手にした本との出会いから、あなたのライフスタイルを見つめます。日々の選択がもっと愛おしくなるかもしれません。

慌ただしい日々の中で、ふと足を止めて本屋さんに入ったり、就寝前のひとときに本のページをめくったり。何気なく手に取った一冊が、まるで今の自分を映す鏡のように感じられること、ありませんか?
私たちの選択ひとつひとつが、自分でも気づかなかった心の機微を、そっと教えてくれるのかもしれません。
今回は、そんな「偶然の出会い」がもたらしてくれた、一冊の本の物語をお届けします。
📝今週のBookPick:「なんとなく」選んだ本が、教えてくれたこと
「50年前の小説が、令和の今、ベストセラーになっている」
2024年の暮れ、NHKのニュースから流れてきたその言葉に、私は思わず耳を澄ませました。有吉佐和子の『青い壺』。 作家の名前は大学受験の現代文で触れたきり。 物語の内容はおろか、タイトルさえもその時初めて知りました。 なぜ、半世紀も前の作品が? その不思議な響きが、小さな棘のように心に残り続けたのです。
年が明け、私は再び会社勤めを始めました。 片道20分、往復40分の通勤。 この時間をどうにか有効活用できないかと考えた時、かつて首都圏で電車通勤をしていた頃の相棒、AmazonのAudibleを思い出しました。 アプリを開くと、あの日ニュースで聞いた『青い壺』がおすすめに現れたのです。 これは何かの縁かもしれない。 私は再生ボタンを押し、耳で読む読書を始めました。
読書という行為は、極めて個人的な営みです。
しかし、いつ、何を、どのように読むかという選択は、その人のライフスタイルと密接に結びついているのではないでしょうか。 私にとって、通勤という生活の変化が『青い壺』との出会いを引き寄せたように、誰かの本棚もまた、その人の人生の局面を静かに映し出しているのかもしれません。
ヒットの裏の、もう一つの物語
物語は一人の陶芸家が生み出した青い壺が、様々な人の手を渡り歩き、数奇な運命を辿る13の連作短編で構成されています。 昭和の香りが色濃く残る会話調の文体は、まるでラジオドラマのようで、オーディオブックで聴くにはとても心地よかった。
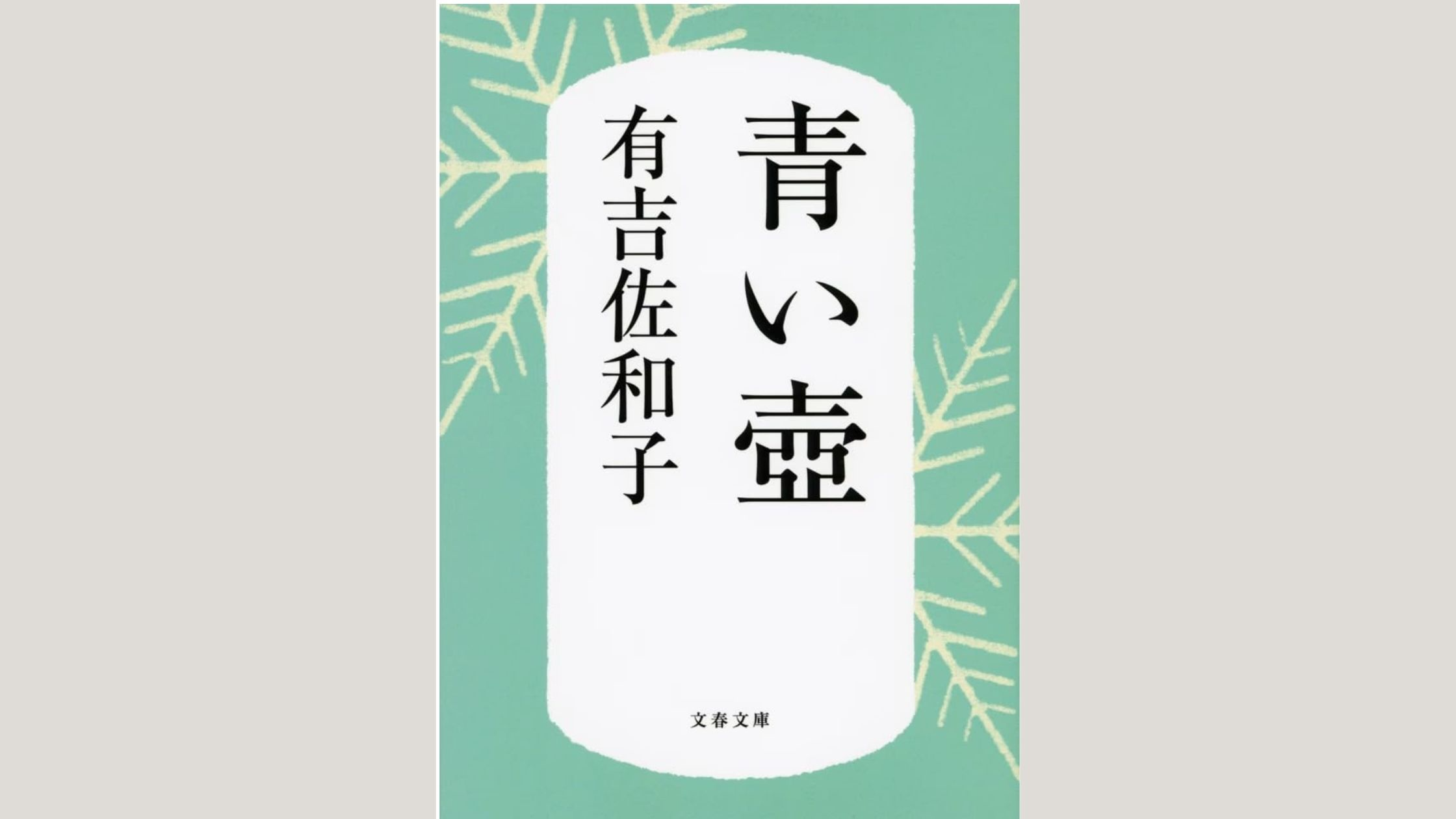
一つ一つの物語は、人間の嫉妬や見栄、愛情といった生々しい感情を描き出し、さながら他人の家のぞき見ているような面白さがありました。
ただ、正直に告白すると、なぜこの作品が80万部を超える社会現象にまでなったのか、その価値のすべてを掴み取ることはできませんでした。 物語の最後に示される、自らの名を捨て去る職人の境地も、私にはあまりに高尚に思えたのです。
なぜ私はこの本を手に取り、多くの人々は熱狂したのでしょう。 調べてみると、そこには巧みなマーケティング戦略やメディア露出がありました。 しかし、そのすべての起点には、一人の編集者の情熱があったという事実に、私は心を打たれたのです。
一度は絶版となっていたこの作品を、文藝春秋の編集者・山口由紀子氏が資料室で「再発見」し、その価値を信じて復刊させました。 その情熱が、作家・原田ひ香氏の「こんな小説を書くのが私の夢です」という熱烈な推薦文につながり、やがて社会を巻き込む大きなうねりとなったのです。 データやAIがヒットを予測する時代に、一人の人間の「この本は面白い」という純粋な情熱が、すべての始まりでした。
その事実を知った時、自分がこの本に惹かれた理由が少しだけわかったような気がしました。 私がニュースで聞いた「50年前の小説が令和に売れている」という言葉自体が、すでに一つの魅力的な「物語」だったのです。
『青い壺』と『54字』の共通点
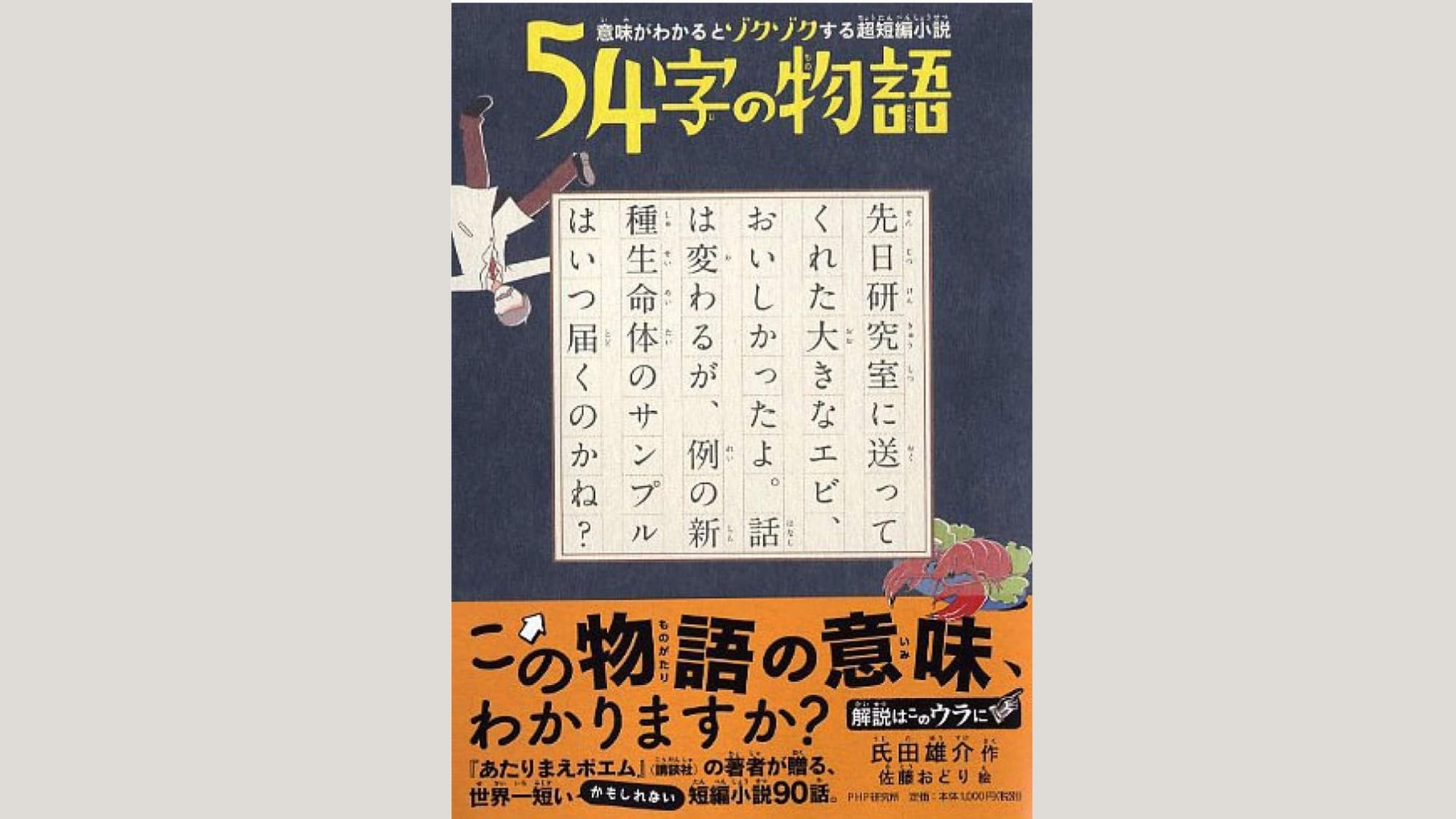
考えてみると、私たちの行動のきっかけは、「流行っているから」という単純な動機であることも少なくありません。 私が最近手に取った、『54字の物語』もその一つ。 9文字×6行の正方形に収まるそのフォーマットは、Instagramの画面に最適化され、ハッシュタグ「#54字の物語」を付ければ誰もが書き手になれる「参加型」の文学です。
「意味が分かるとゾッとする」というキャッチコピーの通り、短い文章に隠された仕掛けに気づいた時の快感は、タイムパフォーマンスを重視する現代人の心を見事に掴みました。
重厚な人間ドラマが描かれる『青い壺』と、刹那的な驚きを誘う『54字の物語』。 一見すると両者は対極にあるように思えます。 でも、そのヒットの背景には奇妙な共通点がある。 それは、どちらも「誰かに語りたくなる物語」を内包していることです。
私たちは何か行動を起こす時、そのものだけでなくそれを取り巻く文脈や、他者と共有できる物語をも一緒に味わっているのかもしれません。きっかけは流行でも、メディアに踊らされた結果でもいい。
一冊の本を迎え入れ、それがもたらす時間を過ごすこと。 たとえその価値がすぐには分からなくとも、なぜ自分はそれを読んだのだろうと思いを巡らせること。 そのプロセス自体が、私たちのライフスタイルを豊かにする、ささやかで個人的な物語を紡いでいくのでしょう。 私の本棚にもまた、そうして迎え入れた一冊の「物語」が加わりました。
💪明日をリデザインするアクション
今週のBookPickが、ご自身の本棚をあらためて眺めるきっかけになったなら、とても嬉しいです。
本棚はあなたが生きてきた時間の証人です。『青い壺』が筆者にとって「通勤」という暮らしの変化と結びついていたように 、そこにある一冊一冊もまた、あなたの人生の様々な局面と響き合っているはず。
この週末、少しだけ時間をとって、本棚から始まる自分探しの旅に出てみませんか?
1️⃣本棚から、気になる一冊を
まずは本棚の前に立ち、ゆっくりと全体を眺めてみてください。そして、今のあなたが「なんとなく」気になる一冊を手に取ります。最近買った本でも、昔大切に読んでいた本でも、どちらでも構いません。
2️⃣本との出会いを、思い出してみる
「この本と、いつどこで出会っただろう?」 その時の情景や、本を手に取った理由を少しだけ思い出してみましょう。誰かからの贈り物でしたか? それとも、自分のためのご褒美だったでしょうか。
3️⃣今の自分へのメッセージを探す
本をぱらぱらとめくってみてください。心に留まる一節や、記憶に残っている場面はありますか? それはきっと、時間を超えて、今のあなたに届けられた大切なメッセージかもしれません。
一つひとつの出会いが、あなただけの物語を織りなしていく。そんな豊かな時間を、ぜひ味わってみてくださいね。
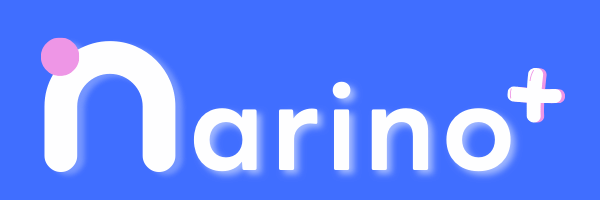

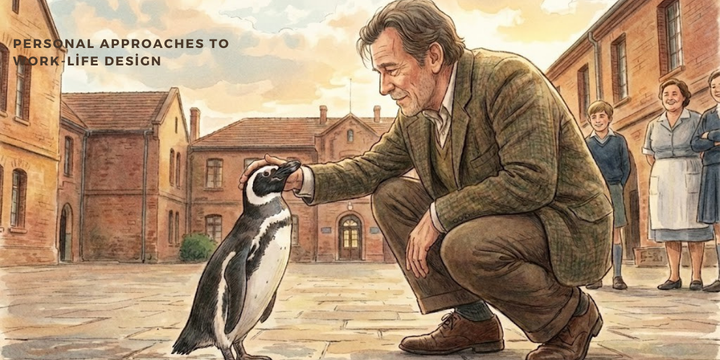


Comments ()