その「優しさ」が壁になる。熊本の学生起業家と壊す、「かわいそう」
「子ども食堂、うちの子は関係ない」と思ってた。熊本で出会った青年が、私の「普通」をひっくり返してくれた話。「かわいそう」というレッテルを剥がし、地域の居場所について考えます。

こんにちは。 のりーです。
今回は、私たちが暮らす「地域」と、そこでの「人との関わり」について、少しじっくりとお話しさせてください。
2024年の春、私たち家族は長年暮らした天草を離れ、熊本市内に引っ越しました。慣れない土地での生活が始まってしばらくした頃、小学校の近くに「子ども食堂」があることを知ったんです。
学校から持ち帰ったプリントを見て、娘が「行ってみたい!」と言う。 そのとき、私の心にふっと浮かんだのは、正直な迷いでした。
「うちみたいな、ごく普通の家庭の子が行ってもいいのかな?」。
なんとなく、そこは「経済的に困っている家庭の子」「特別な支援が必要な子」のための場所だという、漠然としたイメージがあったからです。
でも、運営されている方に思い切って聞いてみると、返ってきたのは意外な答えでした。 「もちろんです!誰でも来てください」。
背中を押されて行ってみると、そこは私が想像していたような「福祉施設」とは違いました。 そこは、困っている誰かのための場所というより、地域の誰もがふらっと立ち寄れる場所だったのです。
「子ども食堂って、誰でも行っていいんだ。むしろ、いろんな人が行くことで、温かい場所になるんだな」 そんな実感を抱いていた矢先、この気づきをさらに深く、そして鮮やかに裏付けてくれる一人の青年と出会いました。
熊本市内で「ふるさと元気子ども食堂」を運営する、学生起業家の宮津航一さんです。
特別扱いも、同情もいらない。ただ「ごちゃまぜ」になれる場所
宮津さんの名前を聞いて、ハッとする人もいるかもしれない。 彼は、2007年に熊本市の慈恵病院に設置された「こうのとりのゆりかご」(いわゆる「赤ちゃんポスト」)に、最初に預けられた経験を持つ当事者だ 。
当時、この「ゆりかご」の設置は国を揺るがすほどの議論を呼んだ。「親の責任放棄を助長する」「命を救う最後の砦だ」。賛否両論が渦巻く中、病院は「赤ちゃんの命を守る」という信念を貫いた。その姿勢は長い時を経て社会の意識を変え、今では一つの道標となっている。
そんな渦中の「第1号」として預けられた宮津さん 。彼は現在、その生い立ちを実名で公表し、活動している 。 その経歴だけを聞くと、私たちは反射的に「大変な人生だったろう」「かわいそうに」という同情のまなざしを向けてしまいがちだ。
しかし、彼と対話し、その真っ直ぐな言葉に触れるにつけ、その「かわいそう」という眼差し自体が、いかに相手を勝手なストーリーに押し込める暴力的なものか、思い知らされる。
「かわいそう」という、やっかいな壁

宮津さんは、里親であるご夫妻のもとで愛情深く育てられた 。 かつて彼が小学生の頃、学校でのトラブルで相手の親から電話がかかってきた際、受話器を握る里親の母は、相手の心ない言葉に対してきっぱりと言い放ったという。
「うちの子は、そんな子じゃありません!」
相手が口にしたであろう「親がいないから」という偏見に対し、自分のこととして本気で怒り、守ってくれた母。それが何よりも嬉しかったと彼は振り返る。
「僕は一度も、自分のことをかわいそうだと思ったことはありません」
その言葉には、一人の人間として尊重され、大切に愛されてきたという揺るぎない土台がある 。そして、「かわいそうではない」自分だからこそできることがあると、彼は前を向く。
「子ども食堂に対して、『あそこに行くと貧困家庭だと思われる』『かわいそうな子に見られる』というイメージを持つ人はまだ多い。でも、その『貧困対策』というレッテルこそが、本当に支援を必要としている家庭の足を、遠ざけてしまっているのです」
これはまさに、私が最初に感じた「うちのような普通の家の子が行っていいの?」という躊躇の正体だった。宮津さんは、この「かわいそう」という壁、支援を阻む見えないレッテルを、社会から剥がそうとしているのだ 。
悲劇を繰り返さないために
彼が活動を始めた大きなきっかけの一つに、2020年4月、福岡県篠栗町で起きた5歳児餓死事件がある 。 当時高校生だった彼は、ニュースでその悲劇を知り、強い衝撃を受けた。
「なぜ、地域社会はそれを防げなかったのか」。これは親だけの責任ではなく、社会のセーフティーネットの問題だと痛感したという 。
孤立を防ぎ、誰かが異変に気づける場所が必要だ 。そう考えた彼は、高校3年生で自ら行動を起こした 。
彼が目指すのは、「特別な子のための場所」ではなく、誰もがふらっと立ち寄れる「地域の交差点」だ 。 どんな子でも当たり前に来て、温かいご飯を囲む。そこには大学生や地域のお年寄りもいる 。
そうした「顔の見える関係」こそが、いざという時に命を守る砦になり 、子どもたちの将来の可能性(機会)を広げる土壌になる 。 子ども食堂は、単にお腹を満たす場所ではなく、地域ぐるみで「人を育てる」教室なのだ 。
福祉の視点が、暮らしを「リデザイン」する
宮津さんのような若い世代が、熊本で地に足をつけ、課題に向き合っている姿。話を聞いていると、地域に関わることは、「誰かのためにしてあげる」というよりも、むしろ自分自身の世界を広げてくれる体験なのかもしれない、と感じます。
近所の子ども食堂はどこにあるんだろう? どんな人がやっているんだろう? そんなふうに少し好奇心を持ってみる。すると、いつも何気なく通り過ぎていた街の景色が、「自分とは無関係な場所」から、体温の通った景色へと変わっていくような気がします。
そして、私たちが無意識に向けていた「かわいそう」「普通はこう」というまなざし。宮津さんの言葉は、そんな自分の心のフィルターに気づかせてくれました。
もし、私たちの何気ない視線が誰かの壁になっているとしたら、その壁を取り払えるのもまた、私たちのちょっとした心の持ちようひとつなのかもしれません。
そうやって想像力を働かせることは、この町で暮らす時間を、もっと愛おしいものにしていくはずです。自分の幸せの物差しが、自分や家族だけでなく、少しだけ地域へと開かれていく感覚。
それは大げさなことではなく、自分の暮らしや働き方を、より自分らしく、心地よく整えていくための素敵な「リデザイン」と言えるのかも知れません。
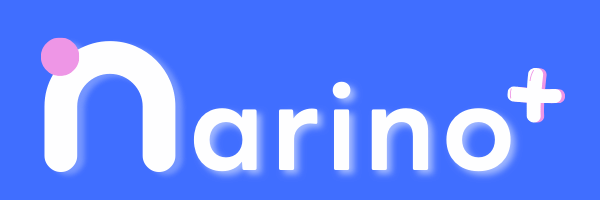

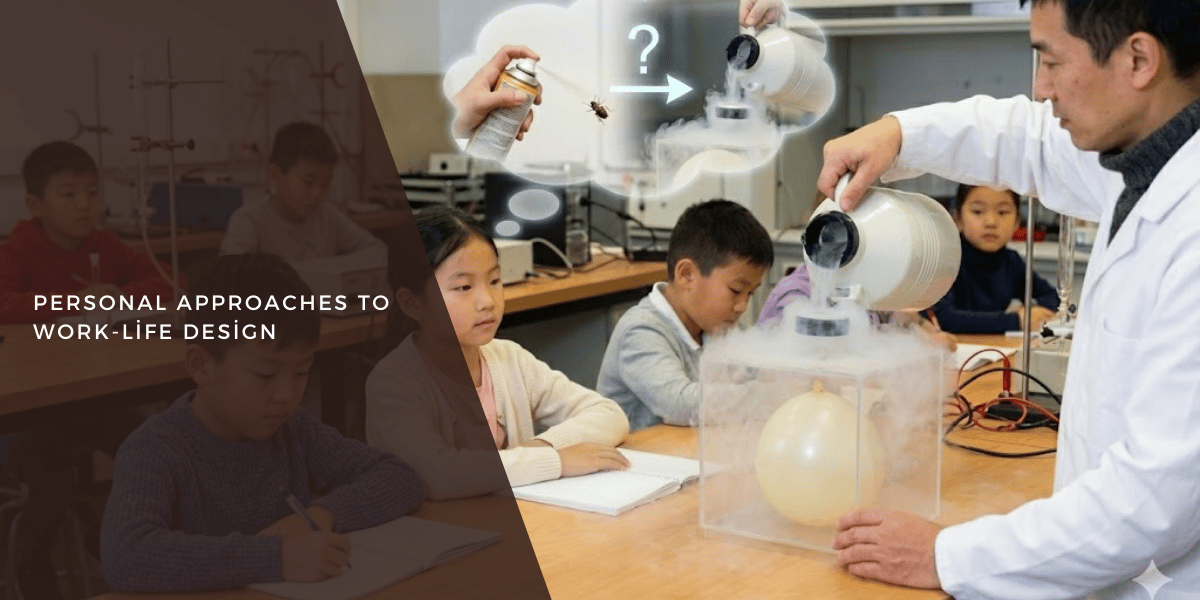


Comments ()