熊本の道が泥に埋まった日。あの国道で考えた、未来の「足」のこと
「地方は車がないと不便」は本当?熊本での水害体験をきっかけに、災害時や老後に潜む車社会のリスクを考察。誰もが安心して移動できる未来のために、当たり前を見直し、持続可能な公共交通のあり方を問い直します。

※この記事は、2025年8月の記録的な大雨(令和7年8月豪雨)について書いています。
「地方は車がないと生きていけない」
移住を考えるとき、あるいは地方での暮らしを語るとき、必ずと言っていいほど耳にする言葉です。確かに、車は便利で、私たちの自由を広げてくれます。
しかし、ある「非日常」を境に、その常識が音を立てて崩れる瞬間があります。
「水の都」熊本市の恵みと、その裏側にあるもの
私の拠点である熊本市は、阿蘇の伏流水が湧き出す「水の都」として知られています。その恵みは全国でも類を見ず、市民の水道水は100%地下水でまかなわれているほどです。
この類まれな水質を求めて、サントリーのビール工場やTSMCの半導体工場が立地するなど、水はまさに熊本の経済と命を支える宝。ですが、豊かな水は時として、猛威を振るう刃にもなります。
水害の歴史を持つ土地柄ということもあり、我が家では「早めの避難」を一つのルールにしています。「大雨が来そうだ」と分かれば、熊本市内の自宅を離れて天草の別宅へ。空振りに終わればそれでいい、という気持ちで移動します。
避難先の天草で直面した、「陸の孤島」の現実
2025年8月、九州を襲ったあの豪雨のときも、私たちは天草へ向かいました。しかし、そこで目にしたのは、避難先もまた「安全」とは言い切れないという現実でした。
雨が落ち着き、国道へ出たときの衝撃は忘れられません。海岸線沿いの道は泥に覆われ、山からの流木と海からのゴミが道を塞いでいました。かつては海だったであろう標高の低いエリアは、冠水し、道路が沈んでしまっている。車を通すことさえできないその傍らでは、入り込んだ泥を懸命にかき出す人の姿がありました。
天草にとって、この国道は島外へと続く文字通りの「生命線」です。代わりのきかない一本道ががけ崩れや冠水で寸断された瞬間、美しい島は外部との接触を断たれた「陸の孤島」へと一変してしまいました。

やっと辿り着いたコンビニの棚は空っぽ。たとえ食料の生産地に近い地方であっても、私たちの日常がいかに遠くからの物流に依存しているか。2011年の東日本大震災直後、首都圏で目にした「物流の麻痺」と同じ光景が、そこには広がっていたのです。
復旧阻む、便利なはずの車
そのとき、熊本市内や天草の各地でもっとも残酷だったのは、放置された車の姿です。冠水した道路で立ち往生し、乗り捨てられた無数のマイカー。それらが緊急車両の通行を妨げ、結果として復旧作業を遅らせる要因となっていました。
私たちの便利な生活は、すべてが「平常時」であるという薄氷の上にかろうじて成り立っている。そう痛感せずにはいられませんでした。
車に過度に依存する社会の危うさは、こうした非日常の場面で鮮明に浮き彫りになります。
「平常時」を基準にしたまちづくりの限界
しかし、この危うさは災害時に限りません。
「地方で公共交通を維持するのはコストがかかりすぎる」という議論があります。ですが、誰もが元気で運転できる「よい時」だけを基準にしたまちづくりは、果たして持続可能なのでしょうか。
私たちは誰もがいずれ年を重ね、運転が難しくなる日を迎えます。その時、移動手段が車しかない社会では、買い物や通院といった当たり前の日常生活を送ることさえままならなくなってしまいます。
私たちが今考えるべきは、目先のコストだけではありません。災害時にも、そして誰もが年を重ねた後にも、安心して暮らせるための「足」をどう確保するか。その答えは、強靭で持続可能な公共交通のあり方にあるのではないでしょうか。
地方にこそ、公共交通を。
泥だらけの国道を見ながら、私はそんなことを考えていました。
未来の私たちが、どこに住んでいても自由に移動し、安心して暮らせるように。今、私たちの手で「未来の足」をデザインし直す時が来ています。
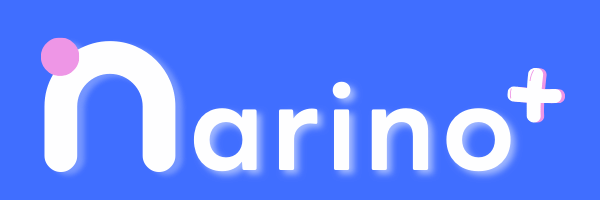

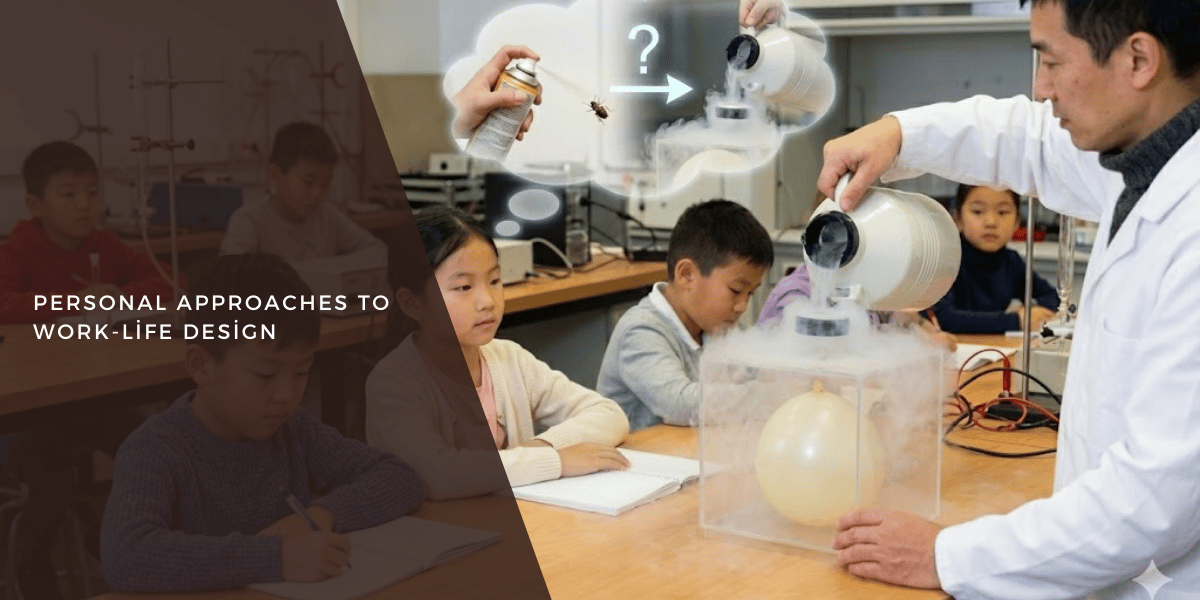


Comments ()