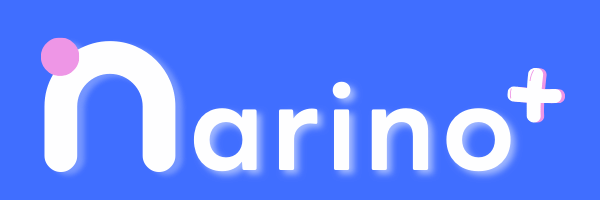観光客には見えない現実。「ここでは無理かも」から再移住へ
実際に足を踏み入れてみると、外から見ていた景色とは全く違う現実が広がっていた。驚くべきことに、オリーブ"だけ"で生計を立てている事業者はほとんどいなかったのだ。

東京から小豆島へ、そして天草へ。理想の農業を求めた脱サラ男の再移住ストーリー。オリーブ農地確保の壁、柑橘農家への転身、場所よりライフスタイルを選んだ記録。
📝今月のリデザイン:突きつけられた選択。開拓民になるか、あきらめるか
「オリーブの島」として知られる小豆島。移住前、私はその美しい風景に魅了され、オリーブ農家として生計を立てる夢を描いていた。しかし実際に足を踏み入れてみると、外から見ていた景色とは全く違う現実が広がっていた。
驚くべきことに、オリーブ"だけ"で生計を立てている事業者はほとんどいなかったのだ。
オリーブは生では食べられない。つまり、なんらかの加工設備が必要になる。オイルにするには搾油機が必要で、小さな搾油機でも数百万、施設全体では数千万もの投資が必要になるのだ。実際、多くの事業者は、海外に契約農園を持ったり、オリーブを使った化粧品開発や観光と組み合わせたりするなど、複合的な経営をしていた。
オリーブは他の作物に比べると高価だが、こうした設備投資まで考えると、実際の利益率は、かなり厳しいものになる。この発見は、農業の収益性について私の認識を根本から覆すものだった。
それ以前に、私の前に立ちはだかっていたのは「ちょうどいい農地が見つからない」問題だった。土地を貸してくれるという申し出はいくつかあった。持ち主はとっくに亡くなっており、次の世代に引き継がれていたものの、相続人も困っているような土地。
つまり「人が手放すのは使いにくいところから」だったのだ。実際にそうした場所に足を運んでみると、開拓民さながら、開墾しなければならない山林ばかりだった。こうした場所が何箇所か続くうちに、だんだんと小豆島での就農が難しいことを悟っていった。
転機となった天草との出会い
小豆島で農地を探しながら将来について模索していた頃、思いがけない転機が訪れた。天草市の視察団が、私が働いていたオリーブ農園にやってきたのだ。