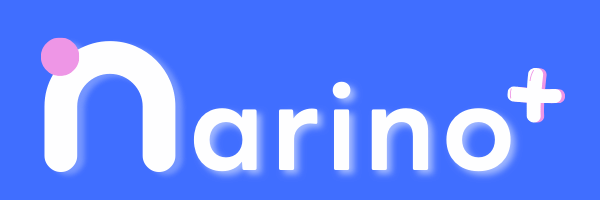価格は誰が決めるのか。デコポンになれなかったミカンが教えてくれたこと
サラリーマンから農業へ。しかし、待っていたのは「なぜ?」だらけの慣習と、「儲からない」という厳しい現実だった。研修では教えてくれなかった経営の視点。JA出荷では価値がないとされた規格外品を、ネットショップで「宝物」に変えた逆転の発想とは?

こんにちは、のりーです。
朝晩はだいぶ過ごしやすくなってきましたね。
今週のテーマは「今月のリデザイン」。前回お届けした、九州の甘い醤油の話、覚えてますか?
暮らしの味付けにカルチャーショックを受けた夫が次に直面したのは、仕事、つまり農業の厳しい現実でした。
今回は、元サラリーマンの夫が農業を始めてぶつかった「収益の壁」と、そこから見つけた逆転の発想についてお話しします。価値がないと思っていたものが、ある視点から見ると「宝物」に変わる。そんな物語です。
研修で学べなかったこと
農業を仕事にすると決めたものの、元サラリーマンの私には知識も経験もなかった。まずは国の新規就農制度を利用し、地域の柑橘農家のもとで研修を始めた。研修の典型的な一日は、師匠から「あそこの畑、草刈っといて」という指示から始まる。朝から夕暮れまで、ひたすら機械と自分だけの時間だった。果樹栽培の場合、収穫期以外のほとんどは地道な管理作業だ。
天草へ移住する前には香川県の農業大学校で土壌や肥料について学び、就農後には長崎の農研機構で柑橘栽培の専門知識を学ぶなど、座学の機会も設けた。
しかし、地域の農家での実地研修も大学校のような教育機関での学びも、その中心は栽培や収穫といった「作業」の方法論だった。なぜこの時期にこの作業をするのか、そして、どうやって売上を立てるのか。そのような問いや実践は、研修のどこにもなかった。作業はもちろん重要だ。しかし、なんのためにやっているのかといえば、商売のためだ。商売のためならば、経営の視点は欠かせない。
昔ながらの農家は、雑草一つない、土が見える状態にすることが良いことだと信じているようで、暇さえあれば草を刈っている。しかし、土がむき出しになり日当たりがよくなると、数日もすれば新たな草が生えてくる。このやり方は、効率的なのか。刈った草を片付けずに、その場に敷き詰めておけば、いわゆるマルチのように新たな草が生えるのを抑制し、土壌の流出も防げるのではないか。誰も「なぜそこまで草を刈るのか」という問いを立てず、慣習として続けていることに、根本的な疑問を感じた。
JA出荷で知った農業の収益性の壁

幸い、私が引き継いだ畑は持ち主が高齢のため離農したもので、すでに柑橘の木があったため1年目から収穫物があった。その不知火(しらぬい)をJA(農協)に出荷して、私は農業の現実を知ることになる。