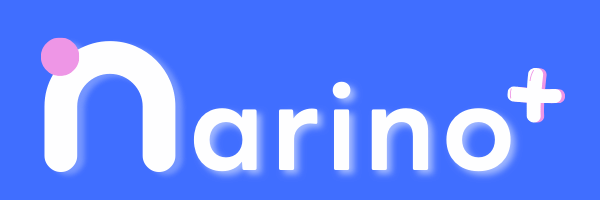天草のミカン農家、AI片手に海外SaaS開発者に物申す
「規格外ミカン」を「宝」に変え、培った「ECスキル」を他者への支援に転用し、「AI」で「言語の壁」を越える。一つの場所で評価されなくても、環境を変え、スキルを応用し続ければ道は拓ける。50代からのキャリアピボット実録。

前回の「価格は誰が決めるのか。デコポンになれなかったミカンが教えてくれたこと」という話は、夫の農業における最初の転換点だったと言っても良いでしょう。
「価値は絶対的なものではなく、環境によって決まる」という、市場原理の実例だと思うからです。
JA(農協)という巨大な流通システムの中では、光センサーが弾いた「デコポンになれない」不知火(しらぬい)は、規格外として1キロ数十円という価格で買い叩かれます。生産者に価格決定権はありません。そこでの価値基準は「見た目の美しさ」と「糖度・酸度の均一性」という、一つのモノサシで測られています。
しかし、その「規格外」を場所を変えて「ネットショップ」という環境に出す。そこで「家庭用」「訳あり」と正直にうたい、光センサーを通していないから甘さの保証はないが、その分デコポンより手頃な価格である、という情報を丁寧に伝える。
すると、JAのモノサシでは価値がなかったミカンが、一般の家庭(特に贈答用ではなく、自分や家族が食べるために買う人たち)にとっては「お得な宝物」へと価値が転換したのです。
この話は人のキャリアやスキルにも当てはまる普遍的な教訓になりえるのではないでしょうか。一つの場所、一つの組織、一つのモノサシで評価されなかったからといって、その人の価値がゼロになるわけではありません。ただ「環境が合わなかった」だけだ、と。
夫にとってこの気づきは、価格決定権を自分の手に取り戻すための大きな武器となりました。しかしこの成功体験は、より本質的な課題を突きつけることになります。
次なる打ち手「フリル作戦」
JA出荷とネットショップ。二つのエンジンを手に入れたことで、私の農業経営はようやくスタートラインに立った。
だが、私は満足していなかった。自前のネットショップだけでは「訳あり品」の受け皿としては機能するが、JAへの依存度もまだ高い。ミカンという「本体」があることを前提に、その価値をさらに高め、売上を最大化し、経営を安定させるための次の打ち手が必要だった。
そのリスクへの対応策として、私は本体の服に装飾を加えるように、「フリルの部分」を複合させることを考え、実践してきた。
フリルその1:「産直プラットフォームへの早期参入」
自前のネットショップだけでは、そもそもお客さんに知ってもらう(認知を得る)ことが難しいという壁があった。そこで有効活用したのが、「ポケットマルシェ」や「食べチョク」といった産直ECプラットフォームだ。 私が登録を始めた頃、これらのサービスはまだ黎明期だったが、その後、創業者のメディア露出やCMといった積極的な宣伝活動によって、知名度を獲得していった。
有名になればユーザー(消費者)も増えるが、同時に私たちのような出店者(生産者)も増える。 後から参加した生産者の中には、なかなか売れないという話も聞く。消費者が新規で買う場合、すでに購入した人のレビュー(実績)を参考にするからだ。生産者の数が多いほど、消費者はどこで買うか迷うため、その傾向は強まるだろう。 実際、私のミカンも、年々、新規よりリピーターの比率が高くなっている。