熊本発、運送会社のDX革命。ベテランを救った「手作りマニュアル」
熊本の運送会社が起こした「コード不要」のDX革命。定年目前のベテランを救ったのは、最新技術ではなく泥臭い「手作りマニュアル」でした。マクドナルドの標準化に通じる、誰一人取り残さないDXの本質に迫ります。

「DX」や「デジタル化」。その言葉に、どこか冷たい響きを感じてはいる人は多いかも知れません。 例えば、マイナンバーカードをめぐる議論の中で、「ついていけない人は置いていかれるのではないか」という不安や疎外感が広がったように。効率化の波は、時に人を置き去りにしてしまう側面を持っています。
けれど、もしデジタル技術こそが、人の温もりや居場所を守る「砦」になるとしたら。
今回の「テックてく歩く」は、そんな固定観念を鮮やかに覆す、熊本のある運送会社のお話です。人とテクノロジーが手を取り合う、その優しい一面についてお伝えします。
「2025年問題」の壁を越える希望
運送業界は今、残業規制による人手不足、いわゆる「2024年問題」の渦中にある。 さらに目の前には、団塊の世代が75歳以上となる「2025年問題」も迫っている。ベテランたちが一斉に引退し、働き手が圧倒的に足りなくなる時代だ。
そんな危機感の中で、ドライバーの安全を守るための「点呼」業務を、24時間365日対面で行い続けるのは、どの現場にとっても至難の業だった。
そこで今回の舞台となる運送会社で導入されたのが、誰でも直感的に使えるシンプルな「遠隔点呼システム」だ。 このシステムが、現場に思わぬ希望を生み出した。
これまで、定年や体力の問題で長距離運転が難しくなった60代のベテランドライバーたちは、豊富な経験を持ちながらも、会社を去らざるを得ない「肩たたき」の対象になりがちだった。彼らの多くはパソコン業務にも不慣れで、事務職への配置転換も難しかったからだ。
しかしこの会社では、仕事を奪うと思われがちなデジタルが、真逆の役割を果たした。専門知識を必要としないデジタルツールが、彼らに「夜間点呼担当者」という、新たな活躍の舞台を用意したのである。
そして、ベテランたちが生み出すその価値は、単なる業務の代替にとどまらなかった。
彼らは元ドライバーだからこそ、画面越しでも仲間の体調変化に敏感に気づける。万が一のトラブルの際には、緊急の応援要員として現場に駆けつけることもできる。
こうした働きは、単なる事務スタッフにはない大きな付加価値であり、彼らは会社にとってまさに頼れる「スーパーサブ」的な存在となったのだ。
成功のカギは「魔法」ではなく「手作り」

この話は、便利なシステムを入れたらすべて解決した、という魔法のような話ではない。 導入当初は、スマホの接続トラブルや、操作に慣れないドライバーからの反発も少なくなかったという。
驚くべきは、そこからの会社の対応だった。 スマートフォンの再起動方法といった初歩的な内容から、図や画像をふんだんに使った分かりやすいマニュアルを作成。さらには、操作方法を説明する短い動画まで自社で手作りし、3〜4ヶ月もかけて粘り強くサポートを続けたのである。
「標準化」こそ、究極の「優しさ」である
この地道な努力の話を聞いて、私はマクドナルドの成功を思い出した。
世界中どこでも同じ品質を提供するマクドナルド。その強さの源泉は、徹底した「マニュアル」にある。ポテトを揚げる時間からピクルスの枚数まで、全ての工程が標準化されているからこそ、経験の浅い人でもプロの仕事ができるのだ。
「マニュアル化」と聞くと、画一的で冷たい印象を受けるかもしれない。 しかし、裏を返せばそれは、「特定の人の能力(属人化)に頼ることをやめ、誰にでも平等にチャンスを開く」という、最も公平で優しいシステムだとは言えないだろうか。
この運送会社が費やした、マニュアルや動画を作るための膨大な時間と労力。それこそが、現代における「マニュアル化」、つまり人に寄り添う「標準化」の実践そのものであった。
誰一人取り残さないためのDX
テクノロジーは、正しく使えば、誰一人取り残さない社会への扉を開く大きな可能性を秘めている。
しかし、その扉を開く本当の鍵は、最新のツールや高度なスキルではない。 この会社が実践したような、丁寧な教育や分かりやすいマニュアル化。つまり、複雑な業務を標準化し、「誰もができる」ようにする泥臭い努力こそが、鍵なのだ。
本当の意味でのDXとは、単にデジタルを導入することではなく、テクノロジーの力で誰もが参加できる仕組みをデザインすること。 「誰一人取り残さない社会」。その実現は、こうした工夫の積み重ねの先にあるはずだ。
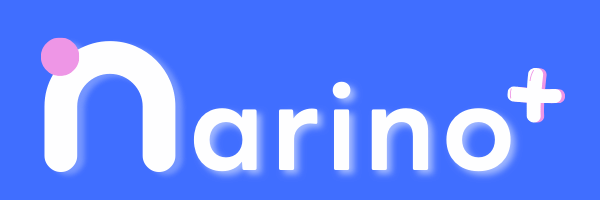


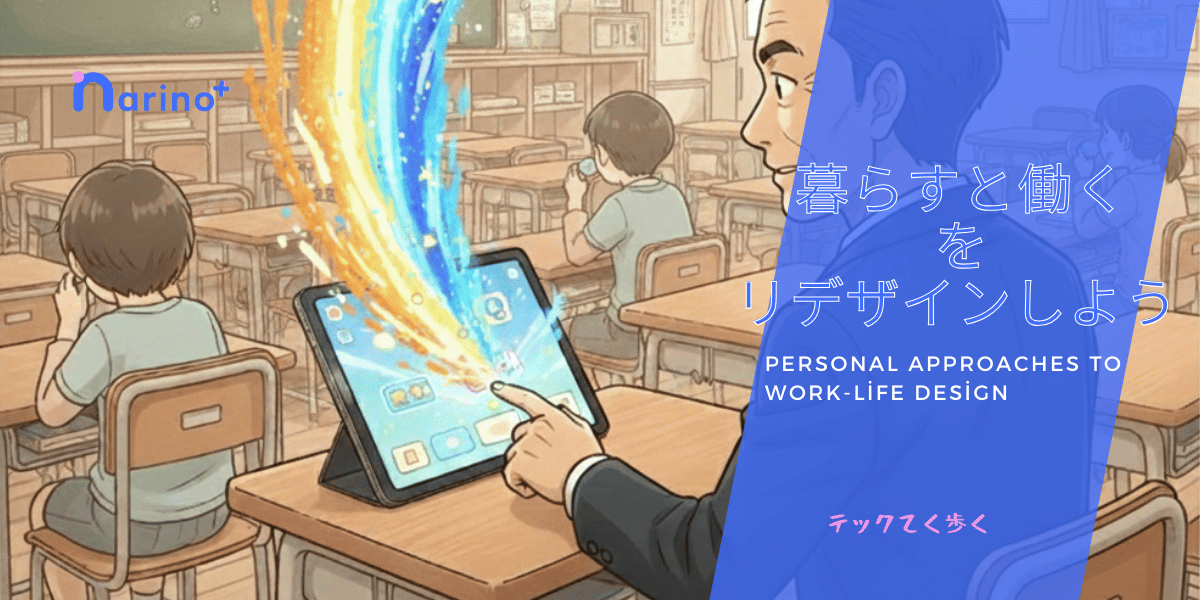

Comments ()